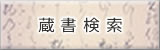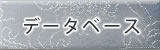古典芸能研究センターは、行吉学園発祥の地である三宮キャンパス(神戸市中央区)にあります。
能楽資料の橘文庫、民俗芸能資料の喜多文庫をはじめ、古典芸能や民俗芸能に関する書籍・資料を幅広く備えた研究施設です。芸能に関連する様々な分野の資料を収集しており、個別の分野はもちろん、より総合的な調査・研究の拠点となっています。
なお、所蔵する資料は、学生・社会人を問わずどなたにもご利用いただけます。
最新情報
- 2025年9-10月の開室日をアップしました。
- 2025年6月から 古典芸能研究センター公式チャンネルで、YouTube版「今月の資料」を公開します。2025年6月の「今月の資料」はこちら
- 「古典芸能研究センター蔵 民俗芸能・民俗資料データベース」を公開しました。
- 2025年5月30日〜7月4日(不定期金曜日・全4回、14時00分~15時30分)、神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ春期講座 古典芸能研究センター共同企画「蔦屋重三郎と浮世絵」を開催します。
最終更新日:2025年9月2日
今月の資料 (2025年9月)
古典芸能研究センター所蔵の様々な資料の中から、毎月1点紹介します。
 大津絵 大日如来図 | 大津絵 大日如来図 志水文庫蔵 一軸 蓮台の上に座し、智拳印を結ぶ大日如来図。蓮台に座して智拳印を結んでいる。智拳印は、胸の前で直立した左手の人差指を右手の拳で握るものである。大津絵には大日如来単独の絵は少なく、貴重な1点である。 大津絵は、江戸時代に大津追分で土産物として売られていた絵である。藤娘などが有名であるが、本来は仏画から始まり、次第に世俗画も描かれるようになった。志水文庫には、仏画4点と神像画2点がある。街道の土産物であった大津絵は、安価な用紙に墨で描かれ、黄土・朱・白緑・紅殻で彩色されるか、あるいは合羽摺りで作られている。軸装の場合は、風帯・一文字などが表装に墨で刷り込まれた所謂描表装で、紐は紙縒り、軸は細い竹というのが基本であった。 |
当サイトのデータについて
神戸女子大学古典芸能研究センターが公開しているすべてのホームページおよびそこに含まれる画像データ・テキストデータ等は、神戸女子大学が著作権を有しており、その扱いは日本の著作権法に従うものとします。これらのデータを、法律で認められた範囲をこえて、著作権所有者に無断で複製・転載・転用することは禁止します。