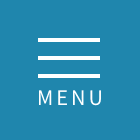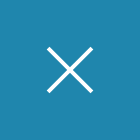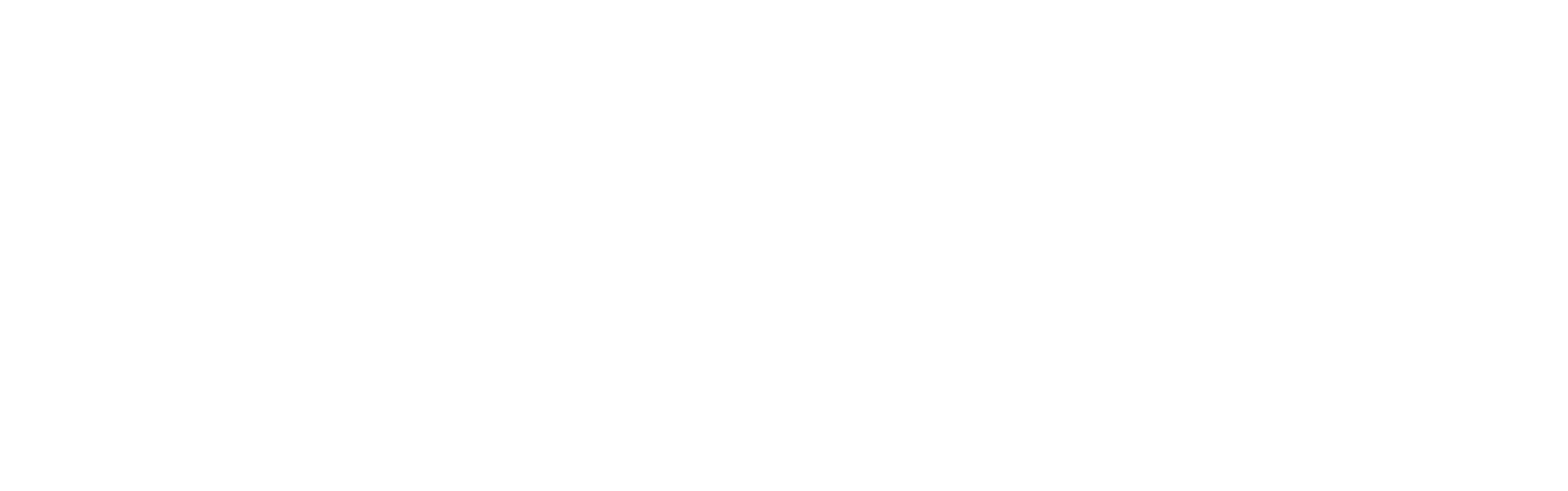
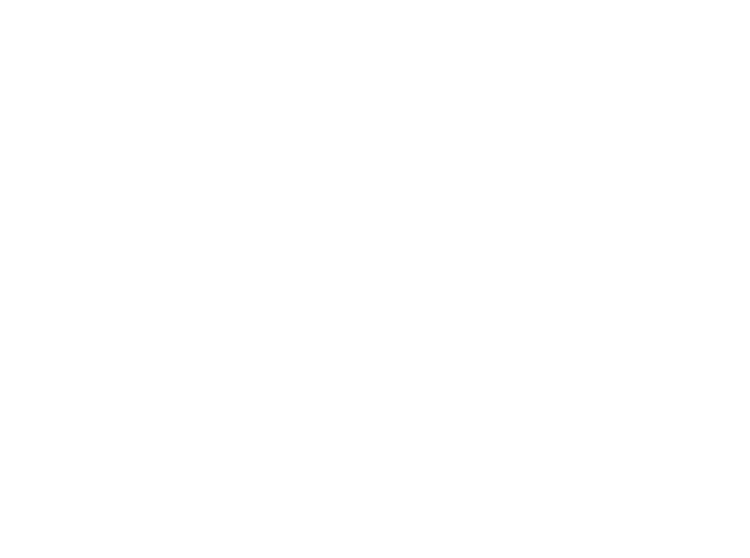
日本史学専攻
専攻概要
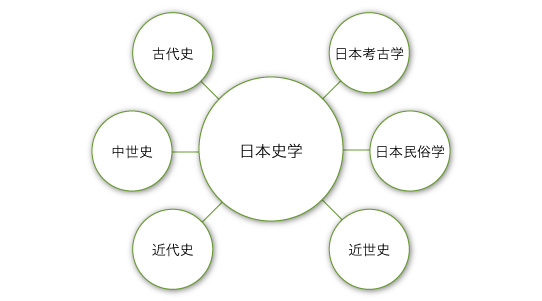
日本史学専攻は古代・中世・近世・近現代の各時代の歴史を探求し、さらに日本考古学や日本民俗学の視点を加え、学部よりいっそう高いレベルの専門研究をおこなっています。
前期課程においては、個別分野ごとの論文作成指導を中心に専門的な講義や演習をおこないます。また、幅広く開講している他の分野の講義や演習、さらには東洋史学・西洋史学の関係科目の受講を通じて、専修免許を持つ教員や、博物館学芸員・資料館職員の養成にも力を入れています。
後期課程では博士号の取得を目指し、よりいっそうの高度な研究指導をおこなっています。
研究環境・カリキュラム
教員陣
日本史・日本考古学・日本民俗学および外国史(東洋史・西洋史)を8名の専任教員が担当します。
各教員は、いずれも学界の最前線に立ち、レベルの高い研究と教育をおこなっています。
カリキュラム
開講科目は「特論」「演習」「特殊研究」に分かれています。「特論」は古代史・中世史・近世史・近現代史・考古学・民俗学など7科目。それぞれの分野で最先端の研究成果にもとづいた講義がおこなわれています。また、それに対応する科目のほか、東洋史・西洋史関係にも「演習」が開講され、研究発表や討論、史料や研究論文の講読演習をおこないます。「特殊研究」では関連科目の東洋史・西洋史の講義もおこなわれます。
博士前期課程 教育課程の概要
| 授業科目 | 担当教員 |
|---|---|
| 日本史学特論Ⅰa・b | 教授 山内 晋次 |
| 日本史学特論Ⅱa・b | 教授 関 周一 |
| 日本史学特論Ⅲa・b | 准教授 尾﨑 真理 |
| 日本史学特論Ⅳa・b | 教授 松下 孝昭 |
| 日本史学特論Ⅴa・b | 准教授 齋藤 瑞穂 |
| 日本史学特論Ⅵa・b | |
| 日本民俗学特論a・b | 教授 川森 博司 |
| 日本史学演習Ⅰa・b | 教授 山内 晋次 |
| 日本史学演習Ⅱa・b | 教授 関 周一 |
| 日本史学演習Ⅲa・b | 准教授 尾﨑 真理 |
| 日本史学演習Ⅳa・b | 教授 松下 孝昭 |
| 日本史学演習Ⅴa・b | 准教授 齋藤 瑞穂 |
| 日本史学演習Ⅵa・b | |
| 日本民俗学演習a・b | 教授 川森 博司 |
| 日本史学特殊研究Ⅰa・b | |
| 日本史学特殊研究Ⅱa・b | |
| 日本史学特殊研究Ⅲa・b | |
| 日本史学特殊研究Ⅳa・b | |
| 日本史学特殊研究Ⅴa・b | |
| 東洋史学特殊研究a・b | 准教授 鈴木 宏節 |
| 西洋史学特殊研究a・b | 教授 吉村 真美 |
| 東洋史学演習a・b | 准教授 鈴木 宏節 |
| 西洋史学演習a・b | 教授 吉村 真美 |
| 論文指導演習a・b | 各担当教員 |
| 学位論文 |
博士後期課程 研究指導の概要
| 授業科目 | 担当教員 |
|---|---|
| 日本史学特論Ⅰa・b | 教授 山内 晋次 |
| 日本史学特論Ⅱa・b | 教授 関 周一 |
| 日本史学特論Ⅲa・b | 准教授 尾﨑 真理 |
| 日本史学特論Ⅳa・b | 教授 松下 孝昭 |
| 日本史学特論Ⅴa・b | 准教授 齋藤 瑞穂 |
| 日本民俗学特論a・b | 教授 川森 博司 |
| 日本史学演習Ⅰa・b | 教授 山内 晋次 |
| 日本史学特論Ⅱa・b | 教授 関 周一 |
| 日本史学特論Ⅲa・b | 准教授 尾﨑 真理 |
| 日本史学演習Ⅳa・b | 教授 松下 孝昭 |
| 日本民俗学演習a・b | 教授 川森 博司 |
| 東洋史学特殊研究a・b | 准教授 鈴木 宏節 |
| 西洋史学特殊研究a・b | 教授 吉村 真美 |
| 論文指導演習a・b | 各担当教員 |
※a=前期開講科目 b=後期開講科目
研究室の特徴
大学図書館には、1969年以来蓄積してきた史学関係の専門図書やマイクロ・フィルムが数多く 揃っており、自由に閲覧することができます。また、大学院研究棟には考古資料室があり、近世史研究室には古文書も収蔵されています。さらに、全教員・院生・学生・卒業生が所属する「神戸女子大学史学会」では、学術雑誌『神女大史学』を発行したり、史跡・博物館・資料館などを見学する研修旅行を実施するなど、院生が活動の中心を担っています
進路
学芸員の資格を活かして博物館・美術館・郷土資料館などに勤めたり、教員の専修免許状を取得して中学・高校の教壇に立つなどの進路があります。このほか、自治体史の編さんや埋蔵文化財関連の業務に従事している修了生もいます。これらはいずれも大学院修了程度の学力が求められる専門性の高い職種で、地域に密着した活動を通して自己の研究テーマを追い続けています。
教員・研究室紹介
教授 川森 博司
研究内容
民俗学とは、日常生活に根ざした「問い」をもとに社会のあり方を再考しようとする学問である。グローバル化する現代社会において、身近な生活の場からの発想をどのように組織していくことができるのかを考えることが、現在の私のフィールドワークの課題である。昔話の語り、観光の場における民俗文化の表現、中高年の人生における民俗の役割などをテーマとして研究を進めている。
教授 松下 孝昭
研究内容
近代日本政治史研究は、中央の政治過程が地方に及ぼす影響と、地方の動向が中央の政局にもたらす規定性との両面から把握されなければならない。そのための素材として、鉄道に着目して研究を進めている。鉄道政策決定過程には、政党・実業家・官僚のほか、軍部も関与しており、加えて地方住民の鉄道敷設要求(地方利益要求)も熾烈であった。したがって、中央政界と地方の動向の双方向から歴史的に分析を加えることで、日本の政治的特質の一端が解明できるものと考える。
教授 山内 晋次
研究内容
7世紀から14世紀頃の日本の国際関係史を研究している。また、その研究と連動して「海域アジア史」という新しい分野の研究も行っている。近年、「東アジア世界」のなかの「日本史」という研究視角の必要性がさかんに主張され、その視角からの論文や著書が数多く公刊されている。しかし、そもそも「東アジア世界」という研究視角自体、さまざまな問題点や疑問点を含んだものである。それを乗り越えて、さらに新しい研究視野を開いていくにはどうすればよいのか。以上ふたつの研究分野を通して、考えをめぐらせている。
教授 関 周一
研究内容
中世日本の対外関係史および海域アジア史を研究している。東アジア海域を構成している地域、例えば対馬、朝鮮の三浦、琉球などに即して、交流の諸相を考察している。交流の要素として、人・物・技術・情報に注目している。倭寇・唐人や漂流人、高級舶来品である唐物(からもの)、鉄砲生産技術、朝鮮人の日本観察などを研究してきた。このような海域交流を背景にした中世日本の外交について、その特質の分析を進めている。
教授 吉村 真美
研究内容
イギリス近代史専攻。19世紀後半以降、選挙法改正や教育改革が進められる中で、国家の未来を担うべき存在として重要視された青少年という年齢集団に注目する。彼らに求められた資質と能力、それを与えるべき学校教育のあり方や具体的なカリキュラム、家族関係と世代意識の変化、産業構造の転換と経済停滞の中での就業、規範からの逸脱行動とそれらの処罰ならびに対処、商業化と大衆化が急速に進んだレジャーの急成長期における余暇活動など、青少年自身と彼らにまつわる諸問題を、同時代の言説から多角的に検証している。
准教授 齋藤 瑞穂
研究内容
土器の研究を基盤に据え、土器型式の運動から、土器を作った人々の動態を読み解く。この「土器社会論」に立脚して、多様な社会が相互に刺激しあった列島弥生時代の実態解明に取り組んでいる。 考古学は現象や事象の発見が注目されがちだが、私はどちらかと言えば、その現象・事象へ到らしめたファクターの発見に関心がある。
東日本大震災で郷里の東北地方が被災して以降は、前近代の大規模災害についても研究を進めてきた。自然現象としての地震や津波でなく、それらが引き起こした災害という社会現象を考古データから追究している。 そうして復興への経過をも射程に入れ、成果をダイレクトに還元する「防災・減災考古学」の体系化をめざしている。
准教授 鈴木 宏節
研究内容
中央ユーラシアの草原遊牧民は、アジア各地を結ぶヒト・モノ・カネ・情報のネットワーク 《シルクロード》 の原動力であり、アジア・東洋のみならずヨーロッパ・西洋の歴史にも影響を与えてきた。私がおもに扱う文献史料は、8世紀前半に現在のモンゴル高原に誕生した突厥文字・テュルク(古代トルコ)語史料 《突厥碑文》 である。これは中央ユーラシアの遊牧民がはじめて残した文学史料であり、これを解読することは、定住農耕民たる漢民族の残した質量ともに圧倒的な漢文テキストを異なる視点から批判することにつながる。このような文献史料の他、自然環境や現地遺跡、各地に残された出土資料を分析の対象とするなど、多様な視点からアジア・東洋の歴史を復元している。
准教授 尾﨑 真理
研究内容
日本近世における所領配置(所領替え)を研究している。特に、江戸幕府の直轄領たる幕領が宛行地の原資となることから、所領替が幕領支配にどのような影響を及ぼしたか、あるいは幕領がそれにどのように対応したかなど、幕領支配との関係に注目している。これによって幕領支配にとどまらず、近世中後期の領主-領民関係像の再構築を目指している。ほかに近世村落を中心とした地域運営や大坂の蘭医学を中心とした幕末医療行政についても研究を進めている。