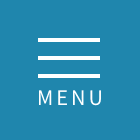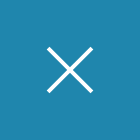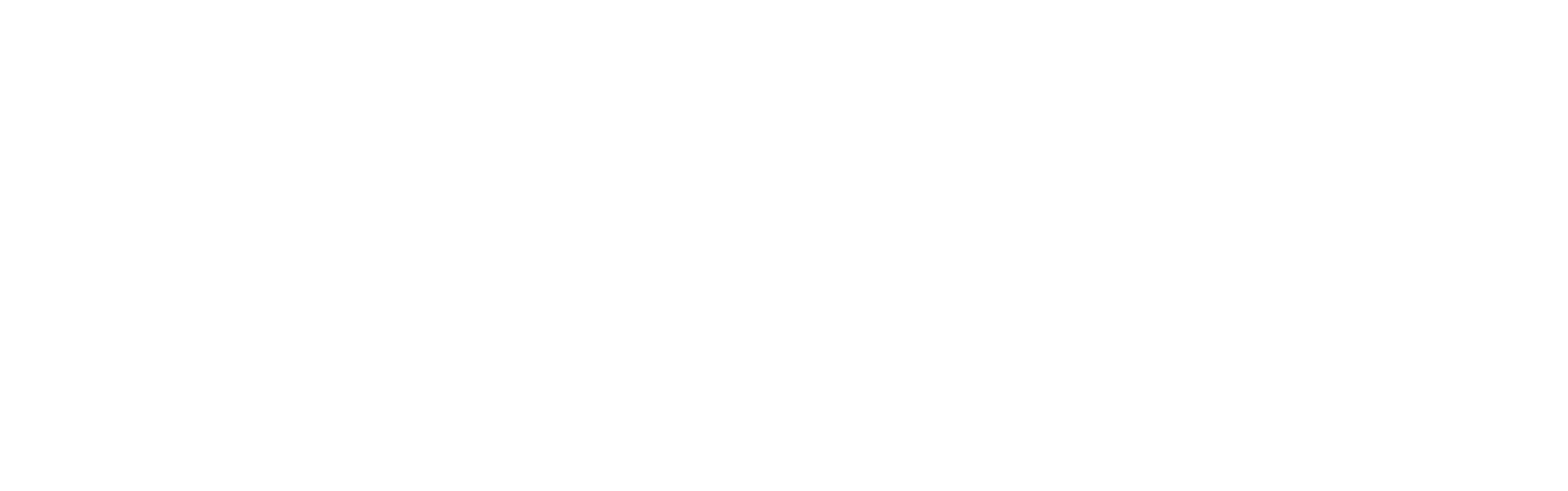
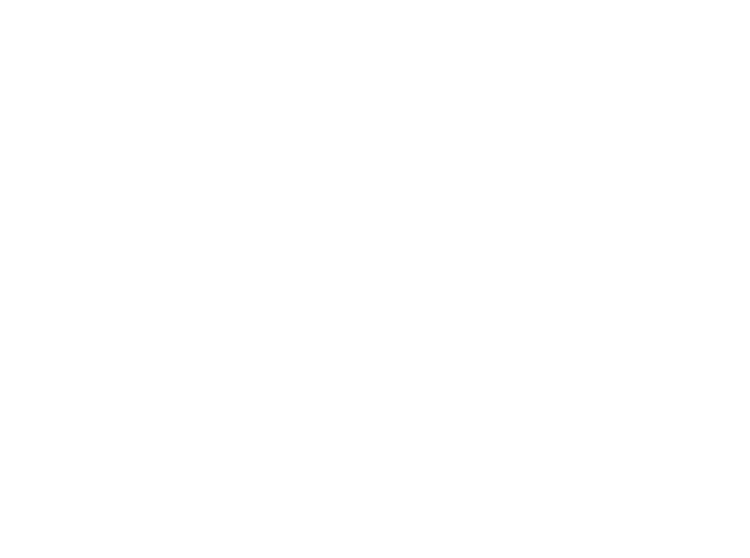
心理学専攻
専攻概要
対人援助職のひとつである心理職は、従来より保健医療や教育、福祉、産業・労働分野等の現場でそれぞれのニーズに応え、実践的に重要な役割を担ってきました。しかし、職責は多様で心理職全体としての社会的立場は十分確立したと言えるものではありませんでした。そのような状況が長年続いた後、ようやく2015年に心理職の国家資格である公認心理師法が成立し、職責が明確になったことで、我が国における心理職の社会的立場が確立しつつあります
心理学研究科心理学専攻では、大学院修了後の公認心理師資格取得とその後の実践での活躍を視野に入れ、公認心理師が主に活動する保健医療、教育、福祉、産業・労働、司法・犯罪の5分野における専門的な心理学的知識と技能に加え、いずれにおいても必要とされるチームアプローチや多職種連携の能力の習得を重視し、社会に役立つ人材の育成を行います。
研究環境・カリキュラム
教員陣
保健医療分野や教育分野、産業・労働分野での臨床経験が豊富な教員が指導を行います。また、学外における心理実践実習においても経験豊富で信頼性の高い指導者に協力を得ています。
カリキュラム
公認心理師法施行規則(2017年)に定められた10科目と450時間以上の心理実践実習のほか、いくつかの特論から構成されています。心理実践実習では、保健医療、教育、福祉、産業・労働、司法・犯罪のそれぞれの分野においても多様な施設で多様な場面を経験することができるようプログラムを組んでいます。
修士課程 教育課程の概要
| 授業科目 | 担当教員 |
|---|---|
| 心理支援に関する理論と実践 | 准教授 山田一子 |
| 保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 教授 池尻義隆 准教授 巣黒慎太郎 |
| 教育分野に関する理論と支援の展開 | 教授 伊藤美奈子 |
| 福祉分野に関する理論と支援の展開 | 教授 伊藤美奈子 |
| 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 助教 曽山いづみ |
| 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 准教授 山田一子 |
| 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | |
| 心の健康教育に関する理論と実践 | (准教授 下司実奈) |
| 神経心理学特論 | 教授 池尻義隆 |
| 心理学研究法特論 | 准教授 佐伯恵里奈 |
| 心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅰ | 准教授 巣黒慎太郎 |
| 心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅱ | 教授 池尻義隆 |
| 心理学演習Ⅰ | 教授 池尻義隆 教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 心理学演習Ⅱ | 教授 池尻義隆 教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 論文指導演習Ⅰ | 教授 池尻義隆 教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 論文指導演習Ⅱ | 教授 池尻義隆 教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 心理実践実習Ⅰ |
教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 心理実践実習Ⅱ |
教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 心理実践実習Ⅲ |
教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
| 心理実践実習Ⅳ |
教授 伊藤美奈子 准教授 山田一子 准教授 巣黒慎太郎 助教 曽山いづみ |
※2026年度入学生の心理学専攻の教育課程を表示しています。
臨床心理センター
本学には臨床心理センターが開設されており、こころの健康の研究・実践拠点として、地域の幅広い年代の方々の悩みについて心理ケア(カウンセリング)を行うほか、近隣の医療機関より心理検査依頼を受け、心理ケアを支える心理アセスメントや、こころの不調を未然に防ぐための予防啓発を行う心理教育に触れる機会を豊富に用意しています。
進路
公認心理師資格を取得し、保健医療分野や教育分野、福祉分野、産業・労働分野、司法・犯罪分野において心理職として活躍する、あるいはさらに他大学院の博士(後期)課程に進学し、その分野の研究者や教育者を目指すことが考えられます。
教員・研究室紹介

- 池尻 義隆 教授 Yoshitaka Ikejiri
専門分野
老年精神医学、神経心理学
研究内容
認知症の症候学や介護者ケアについて研究しています。アルツハイマー病をはじめとする認知症にかかった人では、近時記憶障害、いわゆる物忘れだけでなく、怒りっぽさやひがみっぽさ、まとまりのない行動等の症状がみられます。そして、これらの精神症状や行動変化を生じた認知症の人に接するご家族(介護者)には、戸惑いや否認、焦り、後悔等の心理反応が生じ、これらの心理反応がまたさらに認知症の人に影響し、たいていは悪循環を生じます。
現在の医療や福祉の現場では、ご家族(介護者)に対して診察場面で個別に①疾患教育や②ご家族(介護者)の個々の性格や対処行動に応じた指導、あるいは③家族会などで疾患教育やピアレビューによる心理的支援、④ポジティブ心理学を活かした支援がおこなわれています。しかし、特に②については個々の医療者や介護支援者の経験や技量に委ねられたままで、その知見が広く共有され有効に活用されているとは言えないのが現状です。そこで、②の知見をより洗練し、定式化して普及させることが、より多くのご家族(介護者)の支援に役立つのではないかと考え、研究テーマとしています。
著書・論文、進行中の研究
- 周辺症状(BPSD)への薬物療法. 認知症診療ハンドブック, 医薬ジャーナル社, 2012
- 認知症の脳画像. 看護のための最新医学講座(第2版),第13巻 認知症, 中山書店, 64-73, 2006
- 痴呆. 臨床精神医学講座, 第21巻 脳と行動, 中山書店, 515-532, 1999

- 伊藤 美奈子 教授 Minako Ito
専門分野
教育臨床心理学
研究内容
高校教師という経験を生かし、主に学校教育現場における心理臨床的課題(不登校やいじめ、孤立や自殺など)について、スクールカウンセラーとして心理臨床実践を行っています。実践から得たヒントや疑問を、論文や著作の形で発信していければと思って研究を進めています。それと同時に、教育現場の課題をテーマにした調査研究(文部科学省や内閣府の調査研究を含む)に携わるとともに、国としての政策立案にも参画してきました。
研究方法は、アンケート等を使った調査研究をメインとしていますが、フィールド研究やインタビュー研究にも関心を持っています。
著書・論文、進行中の研究
- 伊藤美奈子編著(2022).『不登校の理解と支援のためのハンドブック-多様な学びの場を保障するために-』ミネルヴァ書房.
- 伊藤美奈子監修(2023).『「学校」ってなんだ?-不登校について知る本-』Gakken.
- 伊藤美奈子(2017).「いじめる・いじめられる経験の背景要因に関する基礎的研究-自尊感情に着目して」教育心理学研究,65,25-36.

- 山田 一子 准教授

- 巣黒 慎太郎 准教授

- 曽山 いづみ 助教 Izumi Soyama
専門分野
臨床心理学、家族心理学、質的研究
研究内容
「離婚を経験する家族への心理支援」というテーマで研究を行っています。離婚は、多くの場合強い葛藤や怒り、悲しみをはらむ出来事です。そして、夫婦間の問題であると同時に、子どもにも大きな影響を及ぼします。もちろん、離婚することが悪いわけではありません。離婚の際に親が子どものことを気にかけて適切に対応してくれることで、子どもは離婚後の生活に適応しやすくなるといわれています。親子それぞれが「離婚」という家族の変化、移行期をうまく乗り切っていけるように応援したい、と考え、研究や実践を行っています。
具体的には、離婚を経験する親子に対する心理教育、FAIT(Families In Transition)プログラムの日本への導入と実践やその効果研究、離婚を経験した親子へのインタビュー調査、高葛藤離婚事例への介入プログラムの適用に関する研究などを行っています。離婚家庭への支援を地域に根付かせていくために、多職種連携や地域との協働にも関心を持っています。
研究手法としては、インタビュー調査をはじめとした質的研究を主に行っています。離婚研究の以前は「小学校教師の初期発達過程」というテーマでインタビュー調査を行っていました。身近な人間関係の中で人々がどう影響しあっていくのか、すれ違ってしまうときはどんなときなのか、いい影響を増やして悪い影響を減らすためにどのようなことができうるのか、に関心があり、研究と実践を続けています。
著書・論文、進行中の研究
- 親の離婚を経験したきょうだいの関係性 曽山いづみ・大瀧玲子 家族療法研究 40(3) 258-266 2023
- 親の離婚を経験した子どもの語りの変化 フォーカスグループインタビューにおける相互作用に着目して 曽山いづみ・山田哲子・本田麻希子 質的心理学研究 23(Special) S53-S61 2024
- 小学校教師の初期発達過程 風間書房 2021